『感想』北海道を開拓したアメリカ人

著 者 藤田文子
出版社 新潮社
出版日 1993年7月15日
212頁
内容
北海道開拓の歴史が、今日でも多くの人々には「青年よ、大志を抱け」というクラーク博士の言葉で象徴されるのはなぜだろうか。
本書は、明治の新政府が北海道開拓を進めるにあたり、風土が似ていると考えられたアメリカから多くの人を雇い入れた歴史をふりかえり、クラークはもとよりケプロン、ライマン、マンロー、ダンなどの足跡をたどってゆく。
一次史料に基づく詳細な記述から浮かび上がってくるのは、北海道開拓に貢献したアメリカ人ひとりひとりにとって、日本滞在が新鮮な異文化体験だったことである。
同じアメリカ人でも、個人的な資質、経歴、来日の動機の違いによって、対日観がさまざまに分かれてゆく過程が興味深く述べられている。
明治初期とは比較にならないほどに密接化した今日の日米関係においても、相互理解の原点は個人的体験であることがあらためて痛感される。
日米文化交渉史のこのエピソードから学ぶべき歴史の教訓は大きい。
(裏表紙 本間長世による)
感想
ブックオフでなんか面白い本ないかな~と探していたら見つけました。
開拓に関する技術を色々集めている現状ですが、過去の開拓事例を知るのも面白そうだ、ということで購入。
それに自分も北海道好きだしね!一応夏に行ったことあるライダーだし!
情勢と動機
西暦1860年代終わり、明治最初期以降、明治新政府はロシアの南下に対する北方警備、石炭や木材などの天然資源の採取、食料の増産などを目的に北海道の開拓を推し進めようとしました。
しかし当時の日本は合理的な開拓に関するノウハウが少なく、また西欧に学ぼうという機運から、数ある列強諸国の中でも開拓の実務経験豊富なアメリカ人を指導者として雇うことにしました。
当時のアメリカは、1860年代前半に起こった南北戦争によってようやくアメリカ国内が統一されたような、ヨーロッパに比べたら歴史の浅い新興国。
アメリカ国内には技術も資源も優秀な人材も多くいましたしアメリカ人はアメリカの良さを認めていましたが、歴史の長いヨーロッパからは認められないようなところだったようでした。
そんなときに自分よりも発展途上国であるにせよ、開拓のノウハウがあり気候が北海道と似ているところが多いとして、日本がヨーロッパ諸国よりもアメリカを選んでくれたことにアメリカは誇りを感じたようでした。
ですので日本から開拓指導の依頼が来た時のアメリカ国内は、ペリー来航以来の日米友好のために発奮するような雰囲気だったらしいです。
新聞などのメディアはアジアの中では先進的な日本のことを賞賛し、日本を「アジアのヤンキー」と呼んでいます。ヤンキーって!褒め言葉なんすよ…一応
日本ではクラークが最も有名でしょうが、実際に大きな力を持ち影響力も大きかったのは、元アメリカ農務省長官のケプロンでしょう。
北海道開拓に力を入れた日本人の代表は黒田清隆(後の総理大臣)でしたが、アメリカにいたケプロンに「誰か良い人紹介してくれ」と言いに行ったら、まさかケプロン本人が来てくれるということに。
流石にケプロン一人ではどうにもならないので、ケプロンから別の有望なアメリカ人にも声をかけていくことになります。
お雇いアメリカ人一人の年俸は色々ありましたが、元アメリカ農務局長であり開拓使の顧問となったケプロンでは10,000ドルほど。
その年俸は、前職の年俸3,000ドルと、当時の日本の最高官職である太政大臣の年俸9,600ドルをしのぐものという、国際的に見ても高給なものでした。
そのような高給にひかれたのもありますが、自分の専門をいかんなく発揮できるという動機を持っていたアメリカ人が多くいたようです。
お雇いアメリカ人たちは開拓を通してアメリカの日本への影響力を強めてゆくゆくは日本支配の踏み台にしてやろう、と思っていたのではなくて、本当に途上国の日本に西欧の素晴らしい技術を広めようと思っていたのがこの本を読んで分かります。
どのアメリカ人も自分の事業を、「将来の発展のための種を蒔いた」という言葉で形容しています。
「北海道はアメリカ人が開拓したんだ」とせず、日本人による北海道開拓の礎になろうとしていたところが、陰謀とか渦巻かない爽やかな感じがして良いですね。
個々人の紹介
この本は、ケプロン、ライマン、クラーク、マンロー、ダンなどのお雇いアメリカ人が残した書籍や手紙、また周辺の人々の彼らへの評価などを通して、その足跡と彼らの考えを辿っていくのがメインです。
アメリカ人と一言で言っても、やはりそれぞれ個性が強いので、日本全体への印象や日本の仕事のしかたなどへの評価は人によって異なっています。
アメリカ人どうしも常に仲が良い、というわけでなく、批難しあったりでなかなかまとまらないことをあったようです。
でもそれがまた人間らしく、人間一人ひとりの目線で北海道開拓を見ていけるような印象を受けます。
彼らの年齢はまちまちでしたが、契約時の年齢が最も高かったのはケプロンの66歳。
やはり一番のベテランでかつ典型的なアメリカ人だけあって、彼の言動が最も標準的なように思えます。
開拓においては、「移住者の自主的な活動が主軸になるべきだ」とケプロンは考えました。
そのため、開拓使の主な役割は環境を改善し公共施設を整備することによって、多くの移住者を北海道にひきつけること。
あくまで開拓の主役は、移住者なのです。
ケプロンはアメリカ農務省勤務時代に節約と能率によって評価されてきた人間だったから、日本の役人の無駄に多すぎるところが気に食わなかったかったようです。
鮭10匹の漁獲に対して一人、農夫一人の監視のために役人一人がついたなど。
現代日本人が聞いても少し耳が痛いものかもしれませんねw
(役人たちは)釘一本を調達するのにも書類をださせたり、現場検証をおこなったり、面倒な手続きを要求するようになった。
ケプロンにはまるで「金を使い、開拓を遅らせるために思いつくあらゆる計画が実行されていった」かのように思われた。
地質鉱山技師のライマンはちょっとクソ真面目なところがあって、ケプロンに「もう少し相手の文化を理解しろ」と言われていたり。
アメリカ南部生まれのダンは貴族的・温情的・階層的な南部人らしい人でしたが、日本に来てからは質素な生活をし、日本人と日本文化に対して謙虚だったり、日本の欧米化に反対していたり。
マサチューセッツ農科大学学長のクラークはアメリカ国内では批難されることもありましたが、札幌農学校の日本人からの評価はものすごく高かったし、クラークから日本への評価も高かったり。
色んなアメリカ人がこの本では紹介されていて誰もかれも優秀そうなのですが、個人的に気に入ったのは、アメリカ南部人のダンでしょうか。
元々アメリカ北部は敬虔、倹約、勤勉を重視しており、南部は温情主義や騎士道精神などを重んじていました。
南部は南北戦争で奴隷制を支持していたから、ダンの日本人への対応はさぞ差別的なのだろう、と読んでいて最初は思っていましたが、むしろ他のアメリカ北部人よりも遥かに日本の日本的良さを重要視していたのが面白かったです。
また、ダンは自分から率先して機械を操縦して泥や穀物にまみれ、お雇いアメリカ人の中でも年俸は少なめ(一番高い時で3,000ドル)で、日本人に対して意見するときは日本人以上に丁重な言葉を用いる、敬語の使い方に厳しく日本人に対しても注意するほど。
結局彼はアメリカに戻ってから外交官になるよう誘われ、晩年は日本で過ごしています。
自由と平等を重視して弱者を切り捨てる北部よりも、南部の人とのほうが(当時の)日本人にとっては付き合いやすかったんじゃないかな?
もし南北戦争で南部が勝っていたら、日本とアメリカの関係性も変わっていたのかもしれない。
全体的に、日本にやってきたアメリカ人は以下のような感想を持ったように思えました。
・日本人個人個人の勉強熱心なところは評価
・黒田清隆を悪く言うアメリカ人はほとんど無し
・ただし、日本のお役所仕事的なところはどのアメリカ人も批判しており、その非効率性と秘密主義に苛立つ人多数
当時の日本人も現代の日本人同様、言外のことや思いやり(忖度?)を重要視していたので、強く自己主張して首を突っ込みたがるアメリカ人との対応には苦労していたようです。
まあ自分もアメリカ人技術者を雇うなら、面倒くさい国内の事務手続きに労力を払われないように配慮したりするかも。
でもそれが「なぜ自分を通さない!」と怒られたりするようで!
北海道移民は当初、貧農や浮浪者が多く、一般的な農民は祖先の土地を離れたり米を育てにくい場所にいくのは嫌がったようです。
移民団のなかで比較的良い成績を収めたのは失業士族移民団らしく、農業経験は少なかったがだからこそ固定観念に縛られず新しいことに挑戦したり、強固な組織力で上手くやっていったようです。
でもそれはアメリカ人の言うところの、「自由で独立した開拓者」とは少し違うものだったらしいですが。
この本で紹介された主だったお雇いアメリカ人たちは、日米の開戦前、1930年代までにほぼ全員寿命などで死亡しています。
歴史の流れを知っていたら、何だか運命的なものを感じます。
個人レベルの開拓に対しては少々視野の大きな本だったと思いますが、それでもやはり「開拓者が持つべき精神」というものを教えてくれるような一冊なのではないでしょうか。



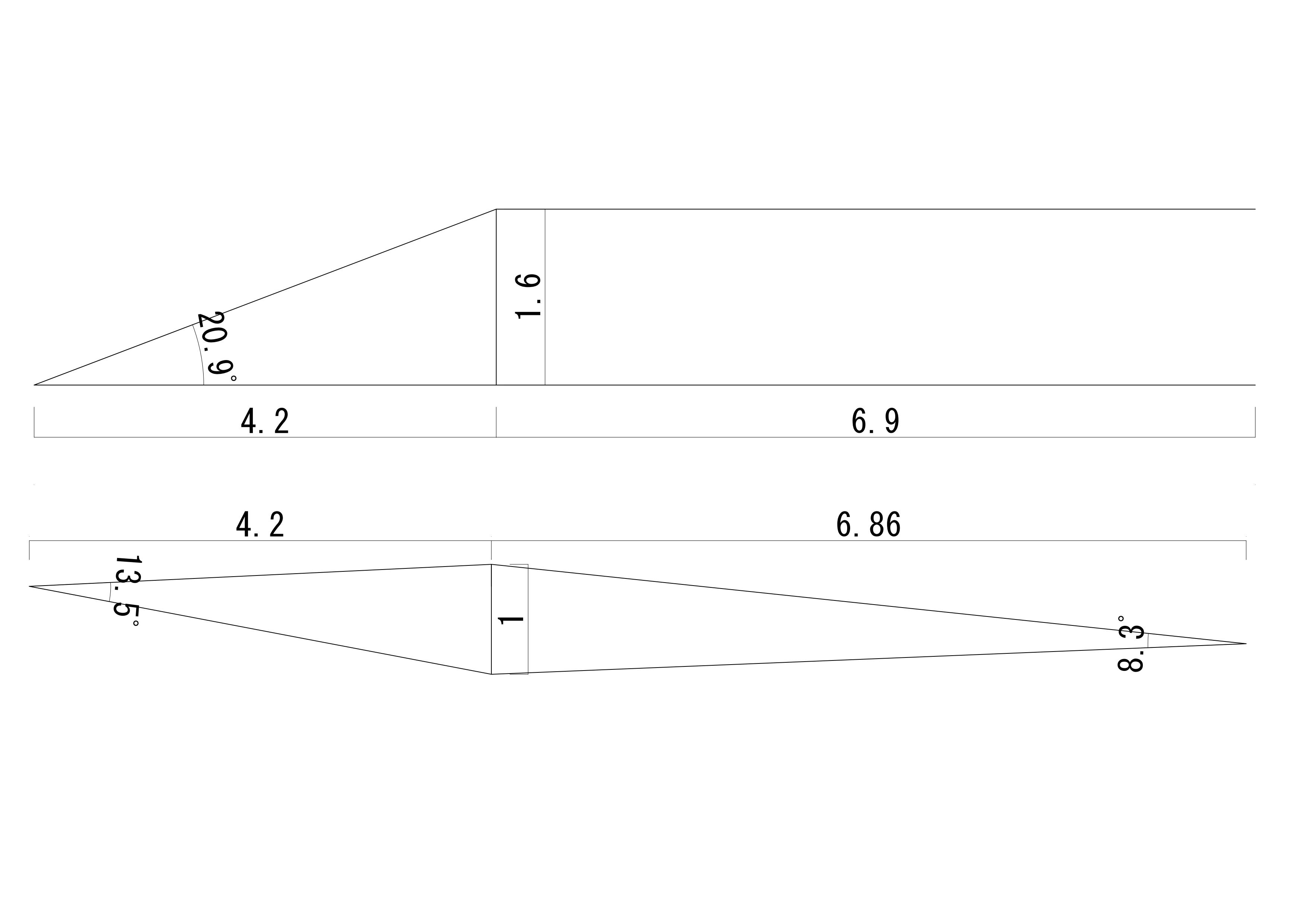










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません