チャージコントローラー・バッテリー周りの接続記録

2018年現在の私の小屋では、24V系600W太陽光発電、計220Ah容量のディープサイクルバッテリー蓄電、24V出力及び定格出力600Wの正弦波インバーターの電気システムとなっています。
この記事ではこのシステムの中でも入力系であるバッテリー・チャージコントローラー・インバーター辺りの接続を主に書いていきます。
図で示すと配線は以下のような感じ。
このように配線すると言っても実際どのような電線を使ってどのように施工すれば良いのかはまた別問題。
第二種電気工事士の資格を取っている私だと言っても、慢心だけはしてはなりません。
まず初めに、配線において最も大事なことは火事を起こさないこと、だと思います。
電線・ケーブルの許容電流量について改めておさらいすると、
- 径が太いものほど許容電流量が大きい。
- 単線(中身が一本の銅線)とより線(細い銅線が集まっている)では単線のほうが許容電流量が大きい。
- 心数が多いほど許容電流量が小さい。
電線の規格は定まっていますから、ネット上でなら簡単に許容電流量を調べられます(例:電線館)
全ての配線を許容電流量の大きい太いもので行ってしまえば電気抵抗も少ないし発熱も少なくなるので特に問題は無いのですが、太いものほどコストもかかってくるので、使用時でも許容電流量を超えずかつ出来るだけ安いもので済ませていく必要があります。
そこらへんの加減は資格勉強だけで身に付くものではないかと思います。
VVF2.0mmでの接続(過去)
2018年3月21日以前では、元々所持していた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)の径2.0mm単線で、バッテリー間、バッテリーとインバーター間、バッテリーとチャージコントローラー間を繋いでいました。
許容電流量は23Aです。
バッテリーとインバーター間には20Aノーヒューズブレーカーを挟んでおり、これで過電流を防ごうとしました。
しかしモーター駆動の椎茸ドリルをインバーターに繋いで使っている時、インバーター内部の35Aヒューズが飛んだ(切れた)ことがありました。
ということはこの許容電流量23AのVVFに35A以上の電流が流れてしまったということです。
このようなことが起こり得る状況ではもう少し許容電流量の大きい配線としなければ、最悪火事が起こってしまいます。
というわけでもう少し許容電流量の大きい配線にしよう、と思い至りました。
単線はより線と違って、中の銅線をペンチなどで曲げて細工することでネジ・ボルト類との接続が簡単に出来ますし、差し込むだけで固定することもしやすいのです。
ただ、単線をあまり太くすると柔軟性が失われてしまうため、頻繁に動かす電源コードなどでは用いられることは少ないです。
接続が簡単で、大電流が流れることが少なく、頻繁に動かすことが無い一般家屋内での配線のほとんどは単線で行われていることでしょう。
実際、ホームセンターなどでも売られている電気部品(コンセントなど)をよく見ると、単線との接続が前提となっているものがほとんどであることに気づくかと思います。
ちなみにネジ・ボルト類との接続時の加工では、右回りになるように銅線を曲げるのが基本です。
左回りに曲げてしまうと、右回しのネジを締める時に緩んでしまいますから!
VCT5.5m㎡での接続
ケーブル(電線)と言っても多くの種類がありますが、入手のしやすさは大きく異なります。
ホームセンターで切り売りされているものもありますが、極太のものはほとんどありません。
DC24Vシステムは通常のAC100Vシステムよりも電圧が低い分、同じ電力であっても流れてしまう電流量が大きいので、極力太いもので配線しなければなりません。
そこで、バッテリー間とバッテリーとインバーター間の大電流が流れる箇所では、ホームセンターで切り売りされているもので最も許容電流量が大きかったVCT5.5m㎡で接続していくこととしました。
許容電流量は41A。
第二種電気工事士技能試験時に購入したVVF用電工ペンチでは被覆を剥けないので、電工ナイフで剥きました。
ケーブル剥くときには中のコードの被覆も切りそうになってしまうので慎重にしなければ…
ケーブルが剥けたら必要な分だけコードの被覆を電工ペンチで剥きます。
5.5m㎡までなら簡単に剥けるものを購入していましたから簡単でした。
剥く長さは必要な分だけ、剥き過ぎたら先端を切り、あまり銅線が露出しないようにする必要あり。
単線と違ってより線では端子を使ったりはんだ付けしたりして接続する必要があります。
単線と違ってすぐにほつれたりして接触不良を起こしたりショートしたりする可能性がありますからね…
インバーター側に使用したのはR5.5-6(5.5m㎡用M6)の丸型端子。
ディープサイクルバッテリー側にはR5.5-8の丸型端子。
丸型端子の大きさも色々あるので、使用する電線とボルトの大きさなどを勘案して選ぶ必要があります。
より線と端子の接続は、電工ペンチで圧着して完了。
はんだ付けより楽ですね。
一応ビニールテープを少し巻いてショート対策をしてみる。
次にバッテリーとインバーター間にブレーカーを取り付けようとしますが、より線ではやはり加工する必要があります。
とりあえず必要な長さに切断して、必要な分被覆剥き。
基本的により線に端子使ってブレーカーのようなものに固定するときは、単線みたいに変換する「ブレード端子」が良いのかな?
しかしホームセンターにも売ってなかったし…
より線を単線っぽくするために、はんだ付けで固めてみることにしました。
昔、電子工作キットの組み立て時に購入したはんだごてとはんだを用意。
固めてみるとこんな感じ。
これで大丈夫なのか!?
はんだで固めた部分でブレーカーと接続。
丸型端子でインバーターやバッテリーと繋げ、電線やブレーカーの位置を少し整えて、こんな感じの配線で終わりました。
バッテリーとチャージコントローラー間は以前どおりVVF2.0mmです。
大電流が流れるのはインバーターとバッテリー間くらいですから、DC24V機器使用時なら基本的にVVF2.0mmくらいで大丈夫だと思います。
というわけで入力系辺りに使用した電線は以下の図のとおり。
今回はより安全な配線方法にするということで、改めて電線の接続方法を調べながら作業してみました。
より線は単線よりも接続方法が面倒だし、資格試験時にはほとんど勉強できないので、第二種電気工事士持ちだからと言ってもちゃんと調べなおさないといけないなと思いましたよ。
また何か不都合あったら改良していく予定です。
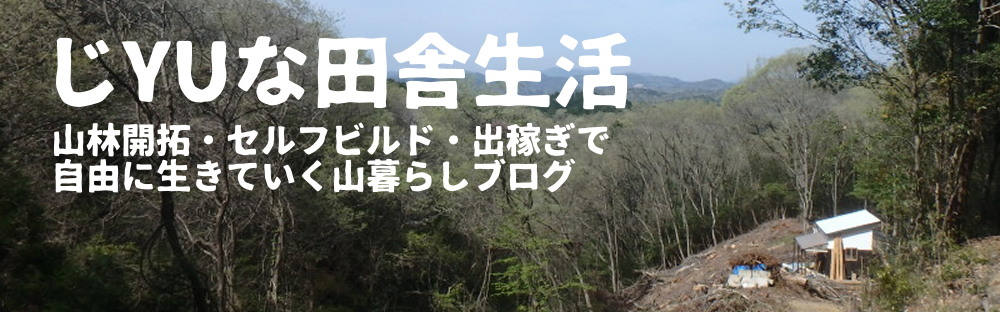

















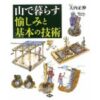








ディスカッション
コメント一覧
12v100Aのバッテリーを2個直列につないだ場合電圧は24Vになりますが電流値100Aは変わりませんが。
100Ahの間違いでは?
より線を半田処理して、単線もどきにして使うのはやめた方が良いかと。
インバーターの最大出力が600wなら、電流は6Aでは?
より線をブレーカーなどに繋げるのはブレード端子使う以外の選択肢は無いのでしょうか?
AC出力側は100V×6A=600⒲になりますが
その時の入力側は600÷24=約25Aとなります。
電圧降下などを考えると10スケ以上使ってもいいのでは?
写真の韓国製バッテリーは20時間率でしょう。能力そんなにありませんよ。
がっかりする人の何と多いことか。
大電流が流れるバッテリーとインバーター間は短いので電圧降下はそこまで考慮しなくて良いかなあとは思ってますが…
今あるモノで作るのなら、丸の端子を圧着し、たたいて棒状に成形すると良いと思う。
あと、買うならこんなのとか↓
TRUSCO 被覆付圧着端子センターピン棒形長さ11.0 TTGVTC1.2511T
説明書にはんだ付けはしないように書いてある理由
脂入りの場合の酸の悪影響
半田は熱で溶ける
地震などの振動で半田はポキット折れ、かえって非安全
裸圧着端子の筒部分を使い上は切断するくらいが妥当
半田か圧着か、ということを調べてみたら色々出てくるのでなかなか面白いものですね。
半田は圧着よりも熱と振動に弱い傾向があり、据え付けブレーカーでそこまで気にするべきかとも考えられますが、別の端子を加工して簡単に取り付けられるなら圧着が良さそうです。
ありがとうございました。
VVFの白は接地線では?(赤につながってますが)