焚き火で付いた煤を再利用して、塗料の油墨にしてみよう

毎日自作のロケットストーブで炊飯しているYUです。
この生活では、焚火キャンプ同様の問題が発生します…
それは、食器に煤が付きまくることです。
キャンプみたいに持ち運ばないので大きな問題にはなりません。
しかし煤が多くなると熱伝導率が悪くなるし、手も汚れやすくなります。
ですのでたまに煤を剥ぎ取っていたのですが、ある日こう思いました。
利用方法が無ければただのゴミでしかない煤ですが、利用が出来ればそれは「資源」です!
何でも利用して「資源」にしていきたい自分ですから、今回は煤を「塗料」にしてみることにしました。
煤を取る
まずは煤を取っていきましょう。
モデルは、毎日米3合炊いている丸型飯盒です。
アルミ製ですが高火力のロケットストーブで使い続けても壊れていません。
安価で、吊り下げ調理が出来るので、焚火キャンプにもおススメの一品かと。
焚火の煤+吹きこぼれの煤化でたんまり溜まってます。
まずはお掃除!
100均で買ったプレートの上で、マイナスドライバーやワイヤーブラシで煤を削り落としていきます。
飯盒はアルミ製ですから、あまりにガリガリやると穴開きそう!
まあどうせすぐに煤は溜まるので、手で触っても汚れないくらいに落ちたら終了です。
プレートの上に落ちた煤を容器の中に入れて、ひとまず保存。
自分はインスタントコーヒーの空容器に入れてます。
間違って飲まないように別の場所で保存してますw
煤を塗料にするために
黒色の煤は、黒色の塗料(顔料)として使用することが出来ます。
代表的なものは膠(にかわ)で固めた「墨」ですね。
墨を液体にしたものが「墨汁」。
墨にも色々な種類があるようですが、それは主に煤の違い。
何を燃やして出来た煤かで、出来上がる墨の性質も変わってくるようです。
他には煤や墨汁に柿渋を混ぜた「渋墨」というものもあります。
古い建築物の中に木材が黒く塗装されたものがありますが、その多くは渋墨のようです。
古来から防腐塗料として使われてたんですね。
お城にも使われてたりします。
で、今回の自分はどうしたかと言うと…
煤と廃油を混ぜて、「油墨」にしてみました。
以前「石谷家住宅」という鳥取県にある重要文化財に行ったことがあるのですが、説明文の中に「部屋全体の木材を、煤を油で練ったもので塗装した」という記述がありました。
今回はそれを真似てみたかったのです。
外側の塗料として使うので、健康面に気を付けなくて良いということで、廃油を使用。
廃油はタダみたいなもん、煤もタダ。
防腐塗料は無料で作れる!
練った油墨を、試しに薪ストーブ式乾燥室の床束に塗ってみました。
油だけ・煤だけだと木材に付着しませんでしたが、練ることで付くようになりました。
触ると手にもねっとりついてしまいますが、触りすぎなければ良さそう。
ちゃんとコーティング剤になってそうだし、木材の中にゆっくり油が浸透していきそうです。
今まではずっとタフソートという防腐塗料を使っていましたが、これからは自給するのも良いですね。
身近なものに目を向けると、案外「資源」って多いんだとも実感。
昔の人は何でも効率よく、循環的に使ってたんだよなあ。
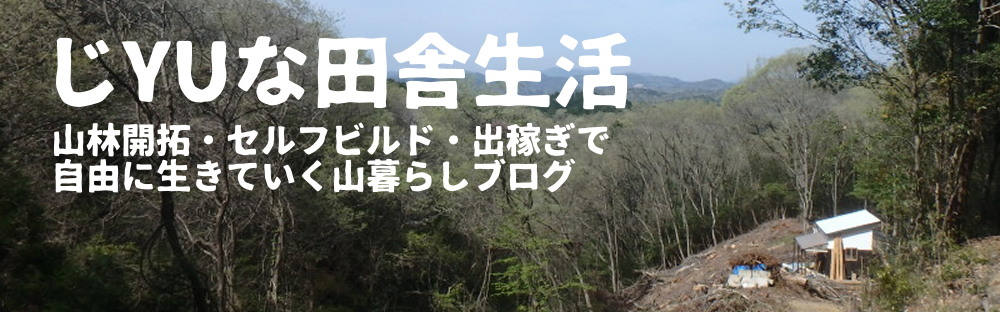



















ディスカッション
コメント一覧
私も同じことを思い、煤を使って絵を描いてみました。
https://youtu.be/01-9o4Q39V8
同じようなこと考える人はいないのかな?とおもい検索してみたらこのページ見つけました。