一斗缶ロケットストーブの解体

製作と運用
1年ほど前に、田舎暮らしブログに影響されて「自分もロケットストーブを作ってみよう!」と思い立って、一斗缶で製作を行いました。
使用したものは以下のとおりです。金額は記録していません…
・一斗缶2個
・Φ106㎜ T曲がり煙突
・Φ106㎜ エビ曲がり煙突
・Φ106㎜ 直筒煙突(長さ900mm程度)
・パーライト
・耐熱土
・アルミテープ
・耐熱塗料
他のロケットストーブ製作記録によると、「高温になるとステンレスが破壊されてパーライトが漏れてくる」ということをよくよく見ているので、試しにエビ曲がり煙突の周りを耐熱土で覆ってみることにしました。
これなら高温になっても土が固まるだけで、パーライトが漏れてくることはないんじゃないか?と期待していました。
運用は主に、実験燃焼と切った枯れ竹の処分に用いました。
正味稼働日数は、およそ2週間程度でしょうか。
枯れ竹を燃やしているとものすごい高温になって、煙突の周りのパーライトが赤~オレンジ色になっていました。
そのような状態で稼働し続けると、直筒煙突の中間辺りが変形し、パーライトが漏れてくるようになりました。
解体
更なる耐久性の確保の研究と、耐熱土の様子を見るために、ロケットストーブを解体しました。
解体前の外観は以下の写真のとおりです。
よく破壊されると言われるエビ曲がり煙突ですが、今のところ異常はありません。
ただ、竹の燃焼時の煙は酸性であるためか、錆が目立ちます。
とりあえずパーライトを取り除きます。
もうこの一斗缶を使う予定は無いので、思い切って大きな穴を開けます。
アルミテープでもロケットストーブの燃焼温度には耐えられないのですが、断熱材の外側にあるテープは無事なようです。
ちゃんと断熱が出来ていた証拠です。
直筒煙突を抜きます。
凹みが目立ちます。
これだけ変形したらパーライトが漏れるのも無理は無いですね。
エビ曲がり煙突周囲の耐熱土は、ある程度固まっていましたが、やはり分解しているとポロポロとはげ落ちてきます。
まあ燃焼時の竹はよく爆発しますから、その衝撃で壊れてしまうのはしょうがないか…
耐熱土は確かにある程度は壊れましたが、完璧に壊れたわけではありませんでした。
特にエビ曲がりとT曲がりの煙突接続部はかなりしっかりしていて、製作当初に私が思い描いていたような効果を発揮できていたように感じます。
パーライトはすべて段ボール箱に入れ、各煙突を一斗缶から外して、分解は終了です。
煙突とパーライトは改良型ロケットストーブにリサイクルするつもりです。
改良予定
やはり耐熱土で煙突を覆っても、持ち運び時の衝撃や燃焼時の衝撃等で破壊される可能性が高いようですね。
もう少し厚みを増やせば壊れないのでしょうが、そうすると重くなってしまいます。
そこで折衷案としては、断熱材にパーライトモルタルを用いること、が考えられます。
パーライトモルタルはモルタルとパーライトを配合したもので、軽さと断熱性と強度がバランス良く保たれます。
また、一斗缶は四角ですから、円形のペール缶のほうが容量の割には断熱効果があるように思われます。
パーライトモルタルを用いてもやはり重くなるので、その量を最小限に抑えるには、断熱効率の良いペール缶を用いるべきと思います。
というわけで、次回はパーライトモルタルを用いたペール缶ロケットストーブの製作を行っていく予定です。
とりあえずペール缶を探さなきゃ…
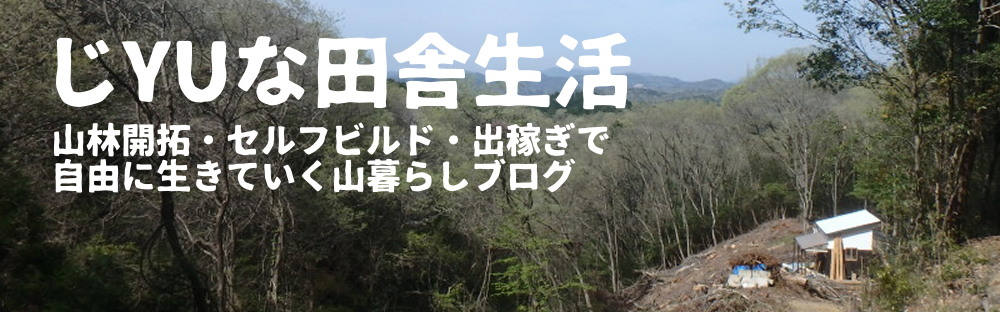















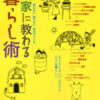







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません